第十三回 『助詞のコンボ技を狙え! ――相性の良い組み合わせ』
- 2023.08.21
- 文法学部 三階教室

ここからは三階教室となります。
二階教室までは初心者向けに俳句のパターンを解説しましたが、三階教室からは一般論を離れて「正解のない問題」を取り上げます。
持続的に作句している読者を対象に、「この話あなたならどう思う?」というスタンスで一緒に考えていくコーナーです。
そのため、これ以降の内容には「筆者はこう考えた」「筆者はこうやってみた」という経験則の紹介が多数出てきます。
結果的に読者の考えとズレていたり、場合によっては正反対の記事になる可能性もありますので、読み進める前にあらかじめご承知おきください。
それでは、筆者の成功や失敗の小噺をお楽しみ頂きつつ、少しでもあなたの参考になることを願って第一回を語りはじめましょう。
俳句のために助詞を語る必要ある?
助詞――
この名を聞いてサブイボの立つ人は五万といるに違いありません。
日本語の助詞の難しさときたら、それはもう異常なレベル。
ネイティブどうしの会話でさえ、「てにをは」の使い方を間違えることもしばしば……
米国国務省の外郭機関によって世界最高の難易度と評価された日本語のなかでも、ひときわ悩ましい品詞のひとつと言って良いでしょう。

かく言う筆者もサブイボ派。
掘れば掘るほど、こんなモノを追求するのは文法ヲタクの所業に思えてきます。(※ あくまで個人の感想です)
本音を言えば見たくもない――にもかかわらず、俳句誌や俳句サイトを眺めていると、「助詞のすすめ」とでも言うべき寄稿をしょっちゅう見かけます。
文法の教本ならともかく、俳句の情報誌でどうして助詞に注目が集まるのでしょうか?
ことさらテーマとされるのには、それなりに理由があるはずです。
そこで、本題に入る前に「なぜ俳句の世界で助詞が重視されるのか?」を簡単に整理しておきましょう。
助詞は俳句の勘どころ
助詞と言えば、自立語同士をつないで互いの関係性をあらわしたり、語句の対象をあらわしたりする付属語の一種。
こう書くと大仰ですが、単独では機能しないので、自立語とくっつくだけの言わば端役に過ぎません。
端役はちょっと侮り過ぎですか?
でも、助詞の小物っぷりは音数からも察せられます。
いわゆる「てにをは」に代表されるとおり、助詞のほとんどは単音からせいぜい数音まで。
もっとも小さな品詞のひとつです。
ぶっちゃけ日常の会話や文書であれば、少しくらい使い方を間違えたところで問題にもならない程度の矮小な存在に過ぎません。
ところが、こうしたの特徴のせい――あるいはおかげ――で、助詞は俳句において最大のパフォーマンスを発揮することになります。
と言うのも、もともと十七音しかない定型俳句では、文中における「一音の比重」が大きくなりがち。
わずかな音数しかない助詞は、その短さゆえに、長大な文章にあるよりも相対的に効果が際立ちやすくなります。
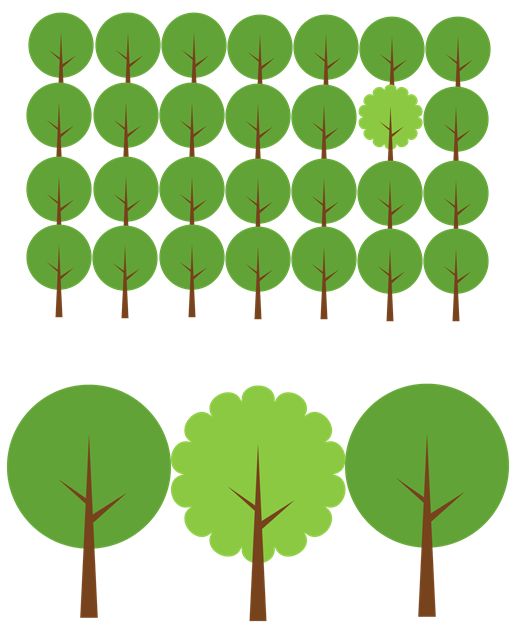
加えて、一句一句がひとつの作品とみなされる俳句では、単品で文意を把握できる構造が不可欠。
前後の文脈という補助装置がないため、一句のなかにある言葉のみで誤解なく意図が伝わらなければなりません。
すると、普段は気にもとめない端役の助詞と言えども、隅々まで厳密に考えて使う必要性に迫られます。

これらが俳句の世界で助詞の重視される背景です。
まとめるとすれば、「俳句ならでは」の性質のせいで、いつもなら問題にならない些細な言い回しが不意にクローズアップされるようなものでしょうか。
・ 音数の比重が大きくなるぶん使ったときに際立ちやすい
・ 前後の文脈から意図をつかめないぶん厳密さを迫られやすい
こうした傾向が強いため、俳句における助詞はことさら注目を浴びるのではないかと考えられます。
コンビネーションで効果倍増!?
ここまでで十分に濃い今回のテーマですが――
さらに悩ましいことに、助詞は文中の言葉が増えれば増えるほど、比例して使用頻度の上がる品詞でもあります。
俳句はだいたい二~四つくらいの言葉で成り立っている場合が多いため、それらをつなぐ助詞も複数セットで用いるケースがほとんどです。
すると、組み合わせた助詞の関係しだいで、セットボーナスか、はたまたコンボダメージか、そうとしか喩えようのない副次効果を生じることがあります。

たとえば、一連の助詞が読み手の印象を変える実例として――
・ 五月雨や大河を前に家二件 与謝蕪村
という蕪村の代表句が挙げられます。
『作り方学部 三階教室 第十三回』でも引用しましたが、助詞のはたらきを見やすいということで、むしろこちらの解説に良く引用される例句です。
ここで使われている助詞をすべて「の」に置きかえても、一応意味は通じます。
テレビのレポーターなどが話すぶんには、たいして違和感を覚えないでしょう。
けれど、「や」「を」「に」とコンビネーションすると、臨場感の違いが頭に残りますよね。
ほかのどんな連結をしてもこうはいきません。
単なる事実の羅列だったものが、一連の助詞によって詩に変わる――こんな具合にニュアンスの違いを生むケースが考えられます。
文法にまったく興味がない人でもなんとなく思い当たるのではないでしょうか?
このように、使いどころや組み合わせしだいで、小さな助詞の存在が少なからぬ影響力を発揮する場面は実在します。
助詞がセットで俳句の勘どころとなる所以です。
以上を念頭において、次章はいよいよ助詞の使い方にフォーカスし、「どんなコンビが俳句の役に立つか?」という法則性へ考察をひろげてみようと思います。
助詞百景、どれを見る?
ここからが本題です。
達人の用例に照らして、上手な助詞の使いどころと組み合わせのパターンを抽出していきます。
無作為に事例をならべても効率が悪いので、まずはどの助詞に注目するか考えましょう。
助詞にもいろいろと種類があります。
格助詞、接続助詞、副助詞……Etc.
個別の説明は専門家に譲りますが、すべてのコンビネーションはこれらが相互作用することによって成立します。
文法上の種類が同じなら、一見どんな文章のどんな組み合わせでもパターンの参考になりそうです。
しかし、それでは俳句における助詞の使い方を語りきれません。
俳句には、小説にも随筆にもない固有の要素があるからです。
もうお分かりかもしれません。切れ字です。
「三大切れ字」だけを取り上げても、「や」は間投助詞、「かな」は終助詞と、三つのうち二つが助詞に該当します。
切れ字は俳句の肝と言っても過言ではない重要区画ですので、これを抜きにして考えるのは金をドブに捨てるようなものです。
こうした理由から、どうせ助詞について考えるなら切れ字に注目すべき、というのが妥当な方向性と考えられます。
「今どき切れ字を多用する筆者の偏った方向性では?」とツッコまれると返答に窮しますが、まったくの的外れということはないでしょう。
セットボーナスを最大化する上でも、重要区画に係るコンビネーションを探るのは好手のはずです。
あとは、どの切れ字を採用するかですが――
上出の「や」と「かな」はいずれも切れ字の代表格ですので、どちらかのパターンを抽出するのが得策と考えられます。
ある程度まとまった数の用例を調べたい事情を考えると、使用頻度の点で「や」を選ぶほうが良さそうです。
そこで、今回は「や」を用いた例句から、助詞の使いどころと組み合わせのパターンを仮定していこうと思います。
シンクロ率から立てる推論
数ある助詞のなかから「や」を取り上げたことで、句中における使いどころのひとつはおおむね既定路線に乗りました。
「上五切れ」です。
一番ポピュラーな「や」の使いどころをパターンの材料とするなら、この位置取りでほとんど異存は出ないでしょう。
問題は、それに何を取り合わせるか? ということ。
文学的な側面から言えば、「や」の役割は強調となります。
十把一絡に「詠嘆」と呼ばれる分類のなかでも、どちらかと言うと感嘆符(!)に近いニュアンスです。
その点を考慮すると、冗長な物言いよりは、語句の関係性を明快に定めたり、対象をビシッと指定したりする相棒のほうがコンビに向きそうです。
ひらたく言えば、「まさにこれは!」の指差し感が理想でしょうか。

これをカテゴリーで括ると――
「係助詞」かつ「とりたて助詞」という結論になります。
「係助詞」はともかく「とりたて助詞」とはこれまた懐かしい(……と言うよりたいていの人が覚えていない?)呼び名ですが、ポイントはこの括りが対比を暗示する機能を含むことです。
要するに、付属した自立語に他者とは違う要素がある点を強調してくれるので、感嘆符(!)に近しい「や」との相乗効果を期待しやすくなります。
この条件に当てはまる候補はいくつかありますが、前章と同様、もっとも使用頻度の高いものを材料に選ぶとなると、助詞「は」の一択となるでしょうか。
すなわち――
<上五末の間投助詞「や」+中七以降の係助詞「は」>
これが最終的なパターンの仮説になります。
「や」と「は」の連携攻撃!
長話もこれで最後。
たどり着いた仮説にもとづいて、過去の用例があるかどうか探りましょう。
言葉の流行り廃れだとか、特定の党派の偏向だとかを避けるため、時代も作風もバラバラの例句をピックアップします。
・ 行く春や鳥啼き魚の目は泪 松尾芭蕉
・ 降る雪や明治は遠くなりにけり 中村草田男
・ あけぼのや泰山木は蠟の花 上田五千石
江戸時代から現代まで、ほかにも相当数の用例を掘り出せました。
中七以降のコンビネーションを「係助詞」かつ「とりたて助詞」というカテゴリーまで広げると、さらに多くの参考事例が見つかります。
ここではバリエーションを誇張するため、あえて「は」の位置取りが異なるもののみ並べましたが、それでも使いどころと組み合わせの法則性はうかがえると思います。
時代も作風もバラバラの達人たちが、そろって<上五末の間投助詞「や」+中七以降の係助詞「は」>というパターンを刻んだ跡があるということは、このコンボ技は使えると判断されたということなのでしょう。

もちろん、なんでもかんでもこれが良いという話ではなく、「や」と「は」のセットが向かないケースもたくさん存在します。
主訴や詠嘆の傾向にあわせて適用しなければならない点には注意が必要です。
ただ、当サイトで再三オススメしてきた「巧い人をマネして上達する」ための指針として、句作の引き出しに入れておく価値はあるかと思います。
筆者をふくめ、助詞に頭を痛めている人たちにとって、こうしたパターンはいくつあっても困りません。
先人の用いた効果を踏襲できるのは大きなメリットなので、今回考察したもの以外にもいろいろ考えてみると面白いのではないでしょうか?
まとめ
今回は日本語最大の難所のひとつ助詞にフォーカスし、俳句における効果的な使い方を考察しました。
助詞は普段から高い意識をもって使われる品詞とは言えません。
しかし、短詩形において大きな存在感を示しやすく、局所的に厳密な取り扱いを迫られるケースが多いため、俳人にとっては軽視しかねる特性を持っています。
また、複数の助詞が互いに影響しあうと、単に文意を通すだけでなく、それぞれの種類に応じた相乗効果を発揮する場合もあります。
以上のことから、俳句へ適切に導入できる一連のセットを見つけ出せば、助詞を苦手とする場合でも効果的に運用できるに違いない、という仮定に立って、使いどころと組み合わせのパターンを考察してみました。
その結果、上五切れに配置した間投助詞「や」と中七以降の係助詞「は」を組み合わせると、強調感に豊んだ構文を作りやすいかもしれない、との推論に至りました。
ひと口で言えば、「や」と「は」のコンボは相性が良さそうだ、という仮説です。
これにもとづいて例句を検証したところ、複数の事例が見つかりました。
近世、近代に比べて切れ字の使用頻度が低下した現代の俳壇でもなお十分な数の用例が見つかるため、ひとつのパターンとして抽出できるのではないか? と意見をまとめたところです。
繰り返しになりますが、これが最良とか、正解とか、そういう類の主張ではありません。
ただ、試行錯誤の結果を先人の知恵に学べるならば、漏れなく拾っておいて損はないでしょう。
複数の助詞を手際よく活かす手段のひとつとして、皆さん自身が考察するときの参考になれば幸いです。
















